
Falco Feedsは、オープンソースに焦点を当てた企業に、新しい脅威が発見されると継続的に更新される専門家が作成したルールにアクセスできるようにすることで、Falcoの力を拡大します。
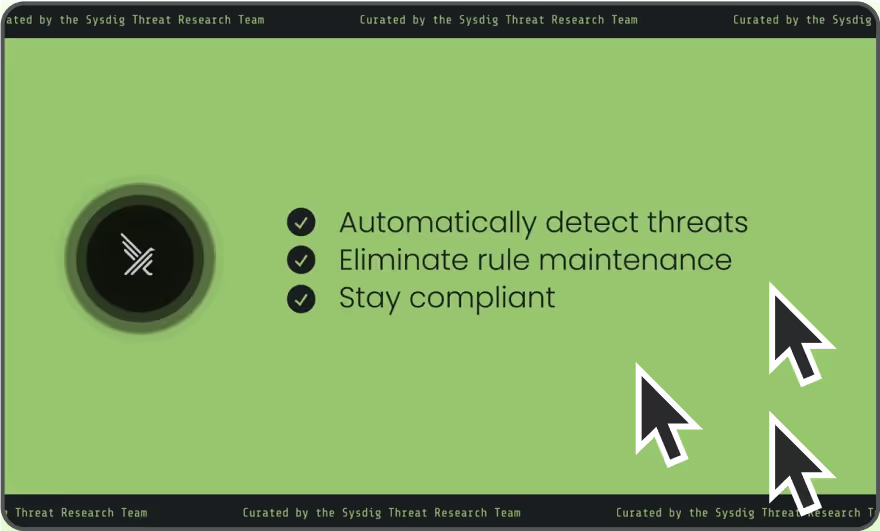
クラウド移行が進む今、環境の変化スピードに人手のセキュリティ管理は追いつきません。
構成ミスや過剰権限、サプライチェーン攻撃など、クラウド特有の脅威は「検知してから対応」では遅すぎます。本記事では、クラウドセキュリティの代表的なリスクと、それを防ぐためのアプローチを、Sysdigの「Code to Runtime」戦略を軸に解説します。CSPM・CIEM・CDRを段階的に活用し、クラウド全体をリアルタイムに守る実践的な方法について理解を深めましょう。
クラウド環境を狙う代表的な脅威
構成ミス
クラウド環境におけるセキュリティ事故の最大の要因は、構成ミスです。
アクセス制御やネットワーク設定、ストレージの公開範囲を誤ると、意図せずデータが外部に露出します。特にS3バケットの公開やセキュリティグループの過剰許可は典型例です。
クラウドは頻繁に変更されるため、一度の設定確認では不十分です。**CSPM(Cloud Security Posture Management)**を活用して構成変更や逸脱を自動検出・修正し、常に適正なセキュリティ状態を維持することが求められます。
認証情報の漏洩
APIキーやアクセストークンの誤公開は、クラウド侵害の出発点となります。
開発者がGitHubリポジトリやCI/CD環境に認証情報を残すと、攻撃者にアカウントを乗っ取られるリスクがあります。漏洩後は数分で被害が拡大し、暗号通貨マイニングや権限昇格に悪用されるケースもあります。
シークレット管理ツールの利用、アクセスキーの定期更新、多要素認証(MFA)の導入に加え、Sysdig Secureによるランタイム監視で不審なAPI呼び出しを検知し、被害を最小化することが有効です。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、開発・ビルド・デプロイの過程で悪意あるコードが混入し、クラウド上に侵入する手法です。依存パッケージやCI/CDパイプラインの脆弱性を突かれると、正規のコンポーネントを介して攻撃が拡散します。
防御には、ソフトウェア署名の検証、依存関係の最小化、脆弱性スキャンが不可欠です。さらに、CDR(Cloud Detection and Response)によるランタイム検知を導入し、実行中のコンテナやプロセスの異常をリアルタイムで監視することが重要です。
コンテナ/Kubernetes特有の脆弱性
コンテナやKubernetes環境では、アプリケーション層と基盤層の両方に特有のリスクがあります。古いイメージの利用、root権限の乱用、APIサーバーの公開設定ミスなどがその一例です。
これらの脆弱性は、コンテナ間の横展開やホスト侵入につながります。Falcoのようなランタイム検知エンジンを活用し、不正なシステムコールや異常操作を即座に検知・遮断することで、攻撃の成立を未然に防ぐことができます。
クラウドにおける脅威の特定方法
クラウド環境の安全性を確保するには、資産・権限・設定・挙動の4つの観点から継続的に監視することが欠かせません。 クラウドは日々変化し、コンテナやワークロードは数分単位で生成・消滅します。静的な設定チェックだけでは追いつかず、リアルタイムに「見える化」し続けることが現代の基本戦略です。
権限と設定の管理
クラウド利用が進むほど、アカウントや権限が増加し、構成ミスや過剰権限がリスクになります。放置されたアカウントや誤設定されたポリシーは、攻撃者にとって開かれた侵入経路になります。IAM(Identity and Access Management)によるアクセス制御と自動監査を組み合わせ、常に設定の適正化を維持します。権限管理は「守る設計」ではなく、「守り続ける運用」です。
クラウド資産と構成の発見
クラウド構成は常に変化し、手動確認には限界があります。設定漏れや誤りは侵入の起点になり得ます。 CSPMを導入すれば、リソースと設定を自動スキャンして脆弱構成を特定可能です。構成の可視化を継続することで、クラウド全体のセキュリティポスチャを健全に保ちます。
過剰権限ユーザーの特定
情報漏洩の多くは、過剰権限が原因です。開発スピードを優先して広範な権限を付与し、そのまま放置するケースは少なくありません。CIEM(Cloud Infrastructure Entitlement Management)を活用し、すべてのID権限を可視化。不要な権限を自動検出・削除し、最小権限の原則(Least Privilege)を徹底します。
アクティブな脅威の検知
クラウド攻撃は数分で進行します。設定変更や侵入を後から検知するのでは遅すぎます。
ランタイム監視を導入し、不審なAPI呼び出しや異常な構成変更を瞬時に検出・遮断。
Sysdig Secureは、CSPM(構成監査)とCDR(ランタイム防御)を統合し、「CodeからRuntimeまで」の可視化を実現します。 「見えないものは守れない」──その原則を具現化するプラットフォームです。
クラウドセキュリティ対策のロードマップ
― 成熟度モデルで考える4ステップ ―
クラウド環境の拡大とともに、企業が直面する課題は複雑化しています。
すべてのリスクを一度に解決するのは非現実的です。重要なのは、自社の現状を把握し、段階的に成熟度を高めることです。
ステップ1:可視化不足 ― 資産と権限の全体像を把握
クラウド全体の構成やアクセス権限が見えていない段階です。
まずは資産の棚卸しを行い、CSPMで構成や権限を可視化しましょう。
ステップ2:構成管理の自動化 ― IaCで安全性と効率を両立
構成の健全性を可視化したら、次は自動化です。
IaC(Infrastructure as Code)セキュリティを取り入れ、脆弱な構成を自動で検出・修復します。 監視中心の運用から「自動制御」への転換が鍵です。
ステップ3:継続的監視と検知 ― 実行時の脅威をリアルタイム把握
構成が整っていても攻撃はランタイムで発生します。Sysdig Secureを使えば、コンテナやワークロードの挙動をリアルタイムに可視化し、不審な操作やマルウェア活動を即座に検知可能です。
ステップ4:統合ガバナンス ― DevSecOpsで「Code to Runtime」を一元管理
最終段階では、開発・運用・セキュリティを統合するDevSecOps体制を確立します。
Sysdig Secureを中核とするSysdig CNAPPを導入すれば、コードからランタイムまでの統合的な可視化と自動防御を実現できます。
Sysdigによる「Code to Runtime」戦略
― 開発から実行までを一気通貫で守る ―
クラウドネイティブ環境では、脆弱性や設定ミスは「コードを書く瞬間」から「実行される瞬間」まで、あらゆる段階で発生します。
Sysdig CNAPPは、この全ライフサイクルを通じて継続的に防御する「Code to Runtime」戦略を実現します。
- Code:IaCテンプレートをスキャンし、構成ミスや過剰権限を検出(Shift Leftセキュリティ)
- Build:コンテナイメージをスキャンし、脆弱性を修正
- Deploy:ポリシーに基づき安全なデプロイを保証
- Runtime:不審な挙動をリアルタイムに監視し、自動封じ込め
さらに、AIアナリスト機能**Sysdig Sage™**がアラートを自動分析し、原因特定から対応策提示までを支援。対応時間を最大76%短縮します。
まとめ ― 「見える化」から始めるクラウドセキュリティ
クラウドセキュリティは、まず**「見えないリスクを見える化すること」**から始まります。
完璧な防御を一度で構築することはできませんが、成熟度に応じて段階的に強化できます。
- 資産と構成の可視化(CSPM)
- 脆弱性と権限の適正化(CIEM / Image Scanning)
- ランタイム防御と自動修復(Runtime / CDR)
リアルタイムでクラウド全体を把握し、「CodeからRuntimeまで」を継続的に守る。 これこそが、Sysdigが提唱する「実践的クラウドセキュリティ」の本質です。
